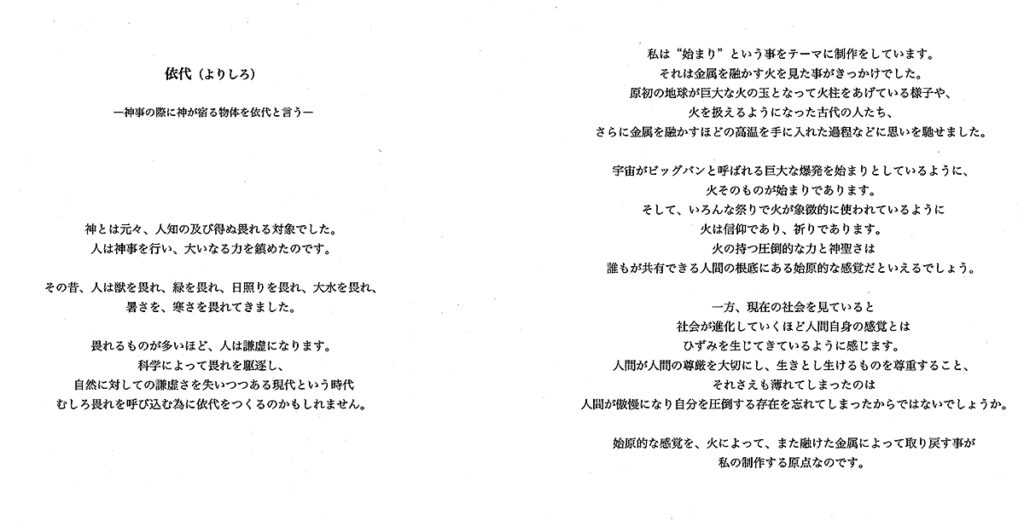SUMII Yasuhiro
2006.7.18 (月)-8.5 (土)
11:00 – 19:00 日祝休廊






角居康宏の芸術
大竹永明
平成15年4月のある日、スキンヘッドの青年が私の勤める美術館に突然やって来た。自分の作品の写真を入れたファイルを持参して「僕の作品を見て批評してほしい、そして助言をしてほしい」と言う。私は背中越しに聞こえてくる同僚とのやりとりに、随分無茶なことを言ってくるな、自分から美術館に売り込みに来る奴なんてロクな奴はいないなと思って聞いていた。
美樹館には、様々な作家たちがあらゆる機会にあらゆるやり方でアプローチしてくる。公立美術館に自分の作品が収蔵されたり、公立美術館が自分の展覧会を開催するというのは、作家にとってステータスのようである。ただしそうした場合には、大抵が何らかの仲介者が介在している。この青年のように、一人で、純粋な気持ちで、無謀に訪れる人間はまずいない。彼が角居康宏君だった。
さほど期待もせず同僚が回覧したそのファイルを見て、「えっ?結構いいじゃない!」と僕は思った。近くの画廊で個展をしているというので、仕事帰りに見に行った。とあるビルの地下の狭いギャラリーでその展覧会は開かれていた。
やっぱりいい。その仕事は洗練さよりも荒削りな強い造形が勝っているが、それがいい。一般に作品は、洗練しようと様式化して型に嵌まっていけばいくほど生き生きとした迫力を失っていく。彼の作品は、彼の謙虚な思いが自然への敬慕と合致して、その思いが見事に造形化されている。芸術としての「かたち」に昇華されている。
僕は、現存作家があまり好きではない。というのも、生きている作家は今の作品が良くても変わっていくものだし、市場で売れてチヤホヤされるようでは、その後の作品も推して知るべしである。また、生きている作家と付き合うのも大変だ。さほどいいと思わなくても本人の前でそうは言えない。言いたくもないお世辞も言わなきゃならない。だから現存作家とは余りお付き合いしないように心がけている。
そういう私がこの作家には魅かれた。
「作品を売るのか」と角居君に聞くと、もちろん売ると言う。私の一番欲しい作品は既に売れていたが、その次にいいと思った作品を買った。
角居くんは私に、「もう(制作を)やめようと思っている」と言った。スキンヘッドの外見に似合わず、彼の性格は随分と内気だということが話しているうちに気がついた。私は、―私がそう言っても何の裏付けもないのを承知で―「君の作品には何か魅かれるものがある。だから大変だけどやめずに頑張った方がいい。」と話した。 そうして角居君の仕事を見続けて3年余が過ぎた。
人間が美術という概念を確立するずっと以前に、人間の心や意識の根底にあった「美しい」という感覚は、人間にはどうにもできない自然の力や運命に対する畏怖や感謝、喜びや悲しみの感情と密接に結び付いているように思われる。いや、そうした人間の理解を超えた絶対的な力に対する人間の感情がまず先にあり、それが昇華されて美しいという感覚に達したのだろう。
人間は、人間の及び得ない絶対的な力を神と定義し、絶対的な力への畏敬、信奉を宗教として体系化していった。西洋は、ルネサンス以降、自然と人間とを対立した関係として捉え、人間の尺度で外界(自然)を解釈していくという人間中心的な世界観に基づいて発展してきており、美術もその例外ではない。翻って東洋では、人間は世界の中心でなく世界の一部であり、自然と人間とは親和すると考えた。こうした自然のおおらかさとそこに抱かれる人間との関係に見る世界観は、山水画など古くからの東洋的絵画観にみられる。
角居康宏の芸術の座標とは、こうした両洋の自然への解釈に至るよりずっと前の、人間の自然に対する驚きや畏敬の念に裏打ちされた無垢な意識のうえに立つ。人間が太古の昔に感じ、そして進歩することで忘れていったこの感覚―自然に対する畏敬の思念―を芸術としてのかたちに完結させたことにある。
角居康宏の芸術の魅力とは、人間の記憶を美術が美術と認識される以前の始原的な感覚にまで遡らせることにより衝撃的であり、我々に与える印象は強烈なのである。
いつから私たちは謙虚な気持ちを失ったのだろう。畏れるべき大いなる存在を無くしたのだろう。
そうした視点に立てば、角居康宏の芸術は、近年の構造主義以降にみられる脱西洋思想から論じることができるかもしれないが、それではあまりに理屈になって詰まらなくなるし、私の手には負えないのでやめる。
「角居康宏は神の手を借りている」
こんなことを書くと角居君に「勘弁してください」と怒られそうだが、私は本気でそう思っている。
(おおたけながあき/松本市美術館学芸員)